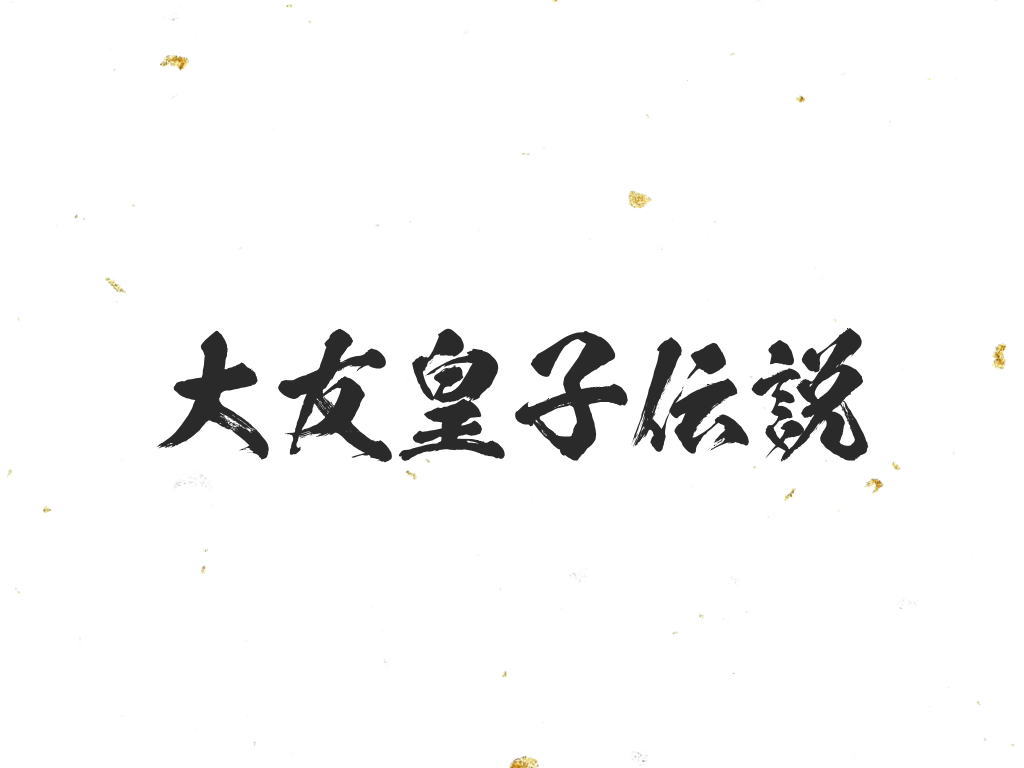神社情報
神社名:神明社
鎮座地:岡崎市上三ツ木町字北島十六番地
御祭神:天照大御神(大日孁貴尊を改める)
旧社格:村社
創 建:弘仁年間(810-23)
境内社:秋葉社、社宮社
参拝日:2016年12月22日
御由緒
社伝に嵯峨天皇の弘仁年間(810-23)村内安全のため氏神として勧請すという。往古はこの地を日久良志の里と称して、開発以来貢祖の取り立ての場所で貢天神ともいう、村名も貢村と号した。この頃の領主平賀四郎の孫平賀十郎右エ門、社地境内を数回寄進したが判別は不明である。その後寛永年中(1624-43)検地の際末置きとなり、慶安二年(1649)領主水野監物の検地帳に旧反別一反二畝十九分、除地と記す。
明治十二年十一月、産土神として据置許可。同三十年四月五日、村社に列格、同四十年十月二十六日、神饌幣帛料供進指定社となる。
愛知県神社庁 発刊
「愛知県神社名鑑」より
参拝記
フタバ産業の六ッ美工場から南に500m程行った集落の北側に鎮座しているのがこの神明社になります。
岡崎市でも特に田園風景が広がっている地区になります。
 田んぼの真ん中を縦断する参道です。
田んぼの真ん中を縦断する参道です。
 参道入口脇には、社号標が鎮座。社格部分が埋められていないオリジナルの形式を残しています。
参道入口脇には、社号標が鎮座。社格部分が埋められていないオリジナルの形式を残しています。
 参道を進み、鳥居越しに社殿を望みます。
参道を進み、鳥居越しに社殿を望みます。
鳥居の両側を常夜燈が挟み込む形で建っています。
その常夜燈の脇には、
 小さな社号標が建っています。たぶんこちらが旧社号標なんでしょうね。
小さな社号標が建っています。たぶんこちらが旧社号標なんでしょうね。
遙拝所
 鳥居を潜って、すぐ左手にある神宮、御陵への遙拝所になります。
鳥居を潜って、すぐ左手にある神宮、御陵への遙拝所になります。
神明社らしく、伊勢神宮への遙拝所なんですね。
手水舎・水盤
 どっしりとしたスタイルの手水舎になります。ここの手水舎にも懸魚が設けられていますね。
どっしりとしたスタイルの手水舎になります。ここの手水舎にも懸魚が設けられていますね。
祓所
 手水舎の奥には、祓所があります。榊が小さいので何代目かの物なんでしょうか。
手水舎の奥には、祓所があります。榊が小さいので何代目かの物なんでしょうか。
狛犬
 昭和11年生まれの狛犬一対です。昭和生まれとなるとかなり装飾がゴテゴテしてきます。
昭和11年生まれの狛犬一対です。昭和生まれとなるとかなり装飾がゴテゴテしてきます。
社殿
 拝殿です。瓦葺き、寄棟、平入、三間幅、この辺りの標準的仕様といった所でしょうか。
拝殿です。瓦葺き、寄棟、平入、三間幅、この辺りの標準的仕様といった所でしょうか。
 社殿全景も見て頂きます。
社殿全景も見て頂きます。
拝殿ー幣殿ー渡殿ー覆殿という配置になります。
境内社
秋葉社と社口社となります。本殿の両脇に一社づつ鎮座しています。
なぜか、秋葉社は切妻平入の社に対し、社口社は寄棟妻入の造りになっていますね。
懸魚&鬼瓦
 鬼瓦と懸魚です。ここ神社の懸魚は鰭付き猪の目懸魚の変形型です。
鬼瓦と懸魚です。ここ神社の懸魚は鰭付き猪の目懸魚の変形型です。
軒丸瓦には貢の文字が。貢村→三ツ木村に変わったのはいつ頃なんでしょうか。
https://amzn.to/2PuEvH3
気楽に読んでいただける一冊です。