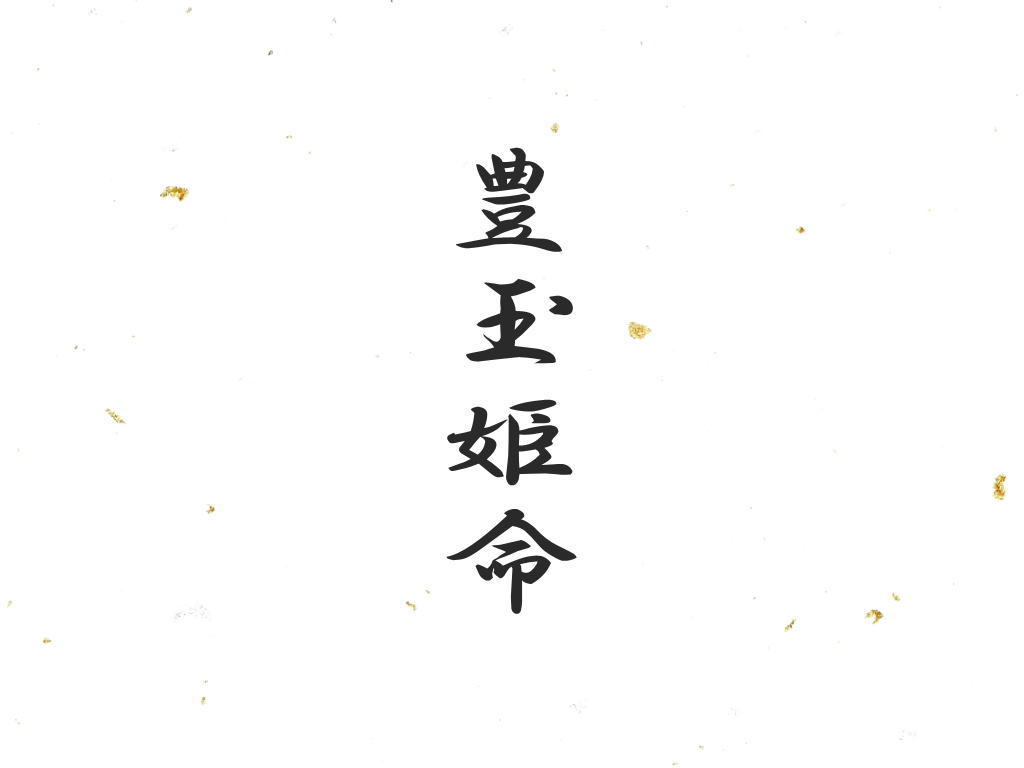ONE POINT
名古屋市中川区長良町に鎮座する八劔社の紹介です。名古屋環状線沿いに鎮座する神社で、江戸時代の桜町天皇の御代に勧請創建されたと伝えられています。
神社情報
| 神社名 | 八劔社 |
| 鎮座地 | 名古屋市中川区長良町四丁目一二九番地(Googlemap) |
| 例大祭 | 十月十日 |
| 創 建 | 不詳 |
| 御祭神 | 熱田皇大神 |
| 旧社格 | 指定村社 |
| 神名帳 | ー |
境内社
| 境内社 | 白山社(御祭神:菊理媛命) 天神社(御祭神:菅原道真) 津島社(御祭神:素戔嗚尊) 秋葉社(御祭神:加具土命) |
文化財
| 国 宝 | ー |
| 国指定 | ー |
| 県指定 | ー |
| 市指定 町指定 村指定 | ー |
参拝情報
| 御朱印 | ー |
| URL | ー |
| 駐車場 | ー |
| 参拝日 | 2022年2月16日 |
御由緒
創建は不詳と伝えるが、愛知県神社名鑑では「桜町天皇の御代(1736-48年)に熱田神宮より勧請、創祀された。」と記されている。
古来より八劔社が鎮座する場所は「長良村」と呼ばれてた。尾張藩は、明暦年間(1655-58年)に藩内の村勢調査に着手。この時の調査書は「美濃国尾州村々覚」のみが現存しているだけだが、その後、寛文年間(1661-73年)に編纂され「寛文村々覚書」が現存しており江戸時代初期の尾張藩の情勢を現在に伝えている。
この「寛文村々覚書」では長良村の事も記されており、その内容の中に「社三社 内 八劔 天神 白山 熱田 与大夫持分 社内壱反六畝七歩 前々除」とある。
この内容を読む限りでは、神社名鑑が伝える桜町天皇の御代より先に八劔社が勧請創建されていた事が読み取れる。
また、現在の八劔社の境内に白山社と天満社が境内社として鎮座している事から、寛文村々覚書で記された天神、白山の各社は八劔社の境内社として遷座している様です。
創建は明らかでないが桜町天皇(1736-48)の頃熱田神宮より勧請し創始すると伝える。明治五年七月村社に列格し、同四十年十月二十六日神饌幣帛料供進指定社となった。
愛知県神社庁発刊「愛知県神社名鑑」
御祭神
- 熱田皇大神
熱田皇大神とは
名古屋市熱田区に鎮座する「熱田神宮」の御祭神。
熱田神宮の創祀の伝承より、御神体は「草薙剣」であるとし、現在では熱田皇大神は「草薙剣を御神体とした天照大御神」であるとする。以前は草薙剣が御祭神であるという考えもあったとか。
御朱印帳の保管に
数年前より非常に集める方が増えた「御朱印」ですが、皆様は御朱印帳はどうやって保管していますか?神社・仏閣を廻って御朱印を受けているとあっという間に御朱印帳の冊数が増えていきますが、そのまま棚などに置いている方が多いのでは?。せっかくお受けした御朱印ですので、日本では古くから着物を始めとして大切なものを保管する為に使われていた「桐箱」に入れて保管した方がよろしいかと思います。
ぜひ、皆様も桐箱に御朱印帳を補完されてみたらいかがですか?
参拝記
中川区四女子町に鎮座する「八幡社」から名古屋環状線を400mほど北上した場所に八劔社は鎮座しています。
境内入口

石灯篭一対、幟掲揚ポール一対、社号標、木製の鳥居が据えられている八劔社の境内入口になります。境内の外周を囲む瑞垣が境内入口部分だけ内側に食い込んでいるのが特徴ですね。
蕃塀

石造の蕃塀になります。彫刻が施されていてかなり重厚感のある造りなんじゃないでしょうか。
手水舎・水盤

木造銅板葺き四本柱タイプの手水舎になります。
二の鳥居

石造りの明神鳥居による二の鳥居になります。
狛犬

生年月が不明な狛犬一対になります。今まで紹介してきた狛犬たちの中でも非常に独創的な姿をしている狛犬になるのではと思います。全体的な造形から思うに明治期から大正期の狛犬だとは思うのですが。
社殿

入母屋造銅板葺妻入りの開放型拝殿を有する尾張造の社殿になります。
そして、拝殿の前に石像の蝋燭立てが据えられています。尾張造の社殿と蝋燭立てはセットと考えていいのかな。

ここ八劔社の社殿の特徴は祭文殿が非常に大きく、さらに祭文殿と拝殿の間に渡りがもうけられている所です。

本殿部分の基壇と祭文殿の位置関係を見ると、祭文殿と本殿をつなぐ渡は後から増築された部分なのかなと思われます。
境内社

白山社 
天神社 
津島社・秋葉社
鎮座地を神社で確認
| 神社名 | 八劔社 |
| 鎮座地 | 名古屋市中川区長良町四丁目一二九番地(Googlemap) |
| 最寄駅 | 電車:あおなみ線「小本駅」徒歩14分 バス:名古屋市営バス「長良町三丁目バス停」徒歩4分 |
ご自宅にお札は祀られていますか?
実家には神棚はあっても、今お住いの所には神棚がない方も多いかと思います。神棚には、日本の氏神である"天照大御神"とご自身がお住いの氏神様のお札を掲げると御神徳が宿るとされています。
賃貸住宅などに住まわれて簡単に神棚を掲げられないという方もお勧めなのが、
南向き、もしくは東向きになる様に、そして目線の高さより上になる様に、棚などの上において頂くとよいかと思います。是非、皆様もご自宅に神棚をご用意いただき、御札を納めてほしいなと思います。