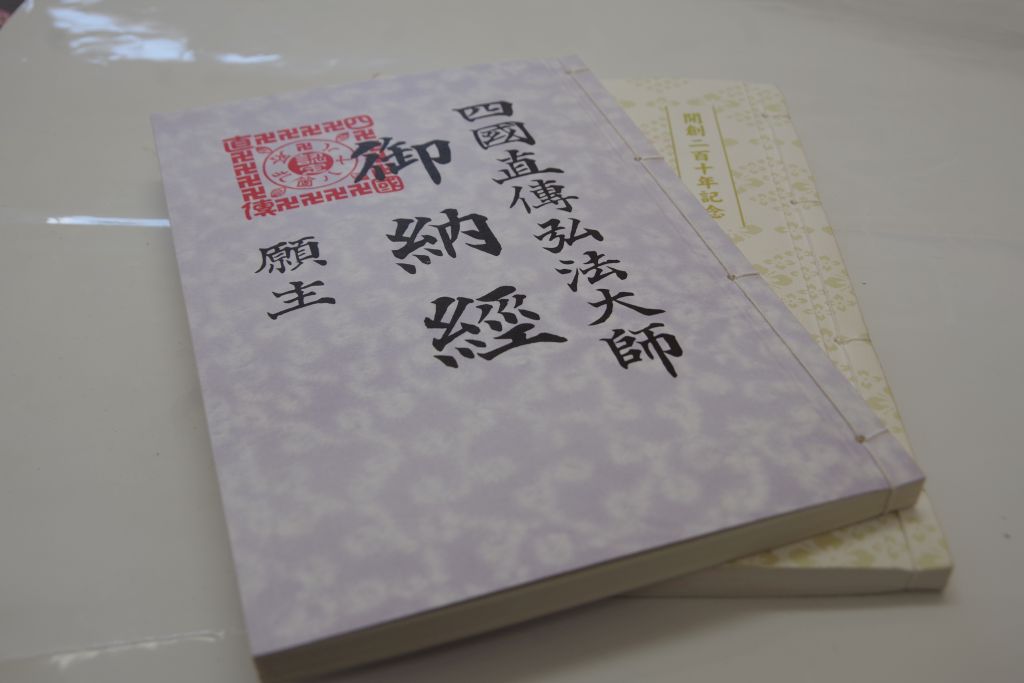千木と鰹木って?
元々は、両方とも上流階級の家などでも使われていたそうなのですが、現代では神社建築のみで使われている様式になります。
千木って?
特に神明造の社殿に見られるのですが、神明造の場合、切妻の屋根の上、両端に斜めに破風板が突き出しており、その飛び出した部分を"千木"と言います。現在では、破風板が突き抜けて作られ作られている千木は伊勢神宮の本殿などを残すのみであとは飾り千木が設けられています。
拝殿の屋根、棟部分に斜めに千木がつけられています。
神社建築用に中空の金物千木があるのかなと思われます。
また、それ以外の造り(例えば、出雲などで見られる"大社造"など)では、千木を棟上に置いている(いわゆる「置千木」)が見られます。
最古の大社造りといわれている神魂神社の本殿です。
切妻、妻入りの本殿ですが、屋根の上にX印で作られた千木が両端に置かれていますね。もともとは棟が浮き上がらないように重石の意味合いもあったそうなのですが、現代では神社建築の象徴の様になっていますね。
そして、千木には男神と女神に応じて、先端の小口の切り落とし方に違いがあります。(あくまでも基本はという話で例外は当然存在します。)
この千木の切り落とし方を”外削ぎ”、”内削ぎ”と言います。
女神の場合、小口を水平に切り落とす事を”内削ぎ”
ただ、なかなか覚えれないと思うので(実際自分も中々覚えれませんでした。)、鬼の角のように上側にとんがっていれば、男神(外削ぎ)であると覚えれば楽かな?と思います。
鰹木って?
大抵の場合、千木とセットで社殿の屋根の上に設けられています。千木単体の場合は見たことありますが、逆に、鰹木のみ社殿の上にある神社は・・・見たことない気がします。
この鰹木、形が鰹節に似ている所からその名が付けられたんだとか・・・。ま「緒木」「堅魚木」「勝男木」「葛尾木」とも書くことがあるそうです。
この鰹木も、千木と同じく棟の抑えとして置かれたのが起源とされています。それがいつの時代にか、本数でこの社殿に鎮座、祀られている神が男神、女神なのかを表す様になったんだとか。
鰹木が偶数だと”女神”
この様に鰹木を載せている神社が多いです。
千木と鰹木の組み合わせ
上記をまとめると、
千木、鰹木の組み合わせ
祭神が男神の場合、千木”外削ぎ”、鰹木”奇数”
祭神が女神の場合、千木”内削ぎ”、鰹木”偶数”
となるはずなんですが・・・外削ぎなのに鰹木が偶数だったり、逆に内削ぎなのに鰹木は奇数なんて神社も時々見かけます。厳格に決められているルールでもなく、自然発生的な風習だったりするので、この辺りは非常にゆるやかな世界だと思います。
ちなみに、伊勢神宮は上記の法則には当てはまらず、独自の様式があるようです。
内宮の祭神が天照大御神、外宮の祭神が豊宇気昆売神と両宮とも女神が最新にも関わらず、内宮では千木・鰹木が内削ぎ10本、外宮は外削ぎ9本となっています。