POINT
名古屋市天白区に広がる相生山。現在は相生山緑地として保全が行われており、名古屋市として貴重な自然が広がる丘陵地域が広がる場所になります。相生山自体は明治から大正時代にかけて文化村として開発が行われ、愛知県下新十名所に選ばれています。
名所情報
| 名所名 | 野並相生山 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区天白町野並地内(GoogleMap) |
愛知県下新十名所
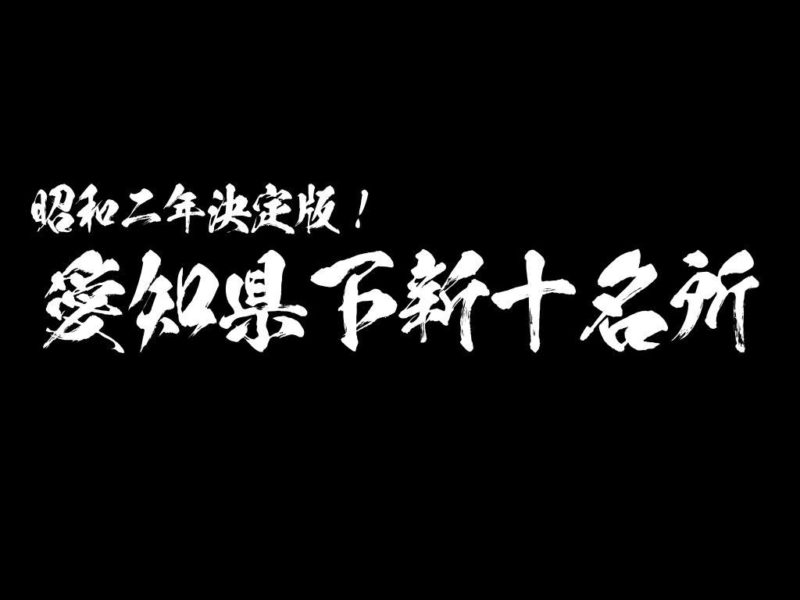
「野並相生山」は昭和二年に昭和二年に新愛知新聞社(現:中日新聞)が読書の方達からの投票によって愛知県の新しい十名所を決定しようという企画「愛知県下新十名所」において「852,631票」を集めて「第5位」になっています。
| 5位/57位 | 852,631票 |
鹿乗橋(愛知県瀬戸市/春日井市)愛知県下新十名所
瀬戸市と春日井市との市境となっている庄内川に架けられた「鹿乗橋」の紹介です。愛知県下新十名所の投票において22位にランクインしており往時はかなり注目を集めていた観光地に架けられたランドマーク的な橋だった様です。
松洞山龍泉寺(名古屋市守山区竜泉寺)尾張四観音
尾張四観音、尾張観音霊場にその名を連ねる名古屋市守山区にある天台宗「松洞山龍泉寺」の紹介です。寺伝では伝教大師(最澄)による創建であると伝えられる古刹であり、また弘法大師(空海)も参籠し宝剣を奉納したとも伝えられています。
愛知県下新十名所と名古屋新十名所を巡る:第2弾ー竜泉寺・鹿乗橋・櫻田景勝・山田元大将之社ー
2022年4月20日、愛知県下新十名所選定にノミネートされた鹿乗橋と龍泉寺を巡るあいちを巡る生活遠征編の立ち寄り先をダイジェストで紹介していきます。
少彦名神社(名古屋市中区丸の内)愛知県下新十名所
名古屋市中区丸の内三丁目に鎮座する少彦名神社の紹介です。江戸時代末期の頃からこの辺りは薬問屋街として発展し「薬祖神」として勧請創建された神社になります。現在でも薬関連の方からの崇敬厚い神社になります。
愛知県下新十名所と名古屋新十名所巡り ー京町薬祖神・闇之森・榎ノ権現・久屋金刀比羅社ー
2022年4月13日はどこ行こう 令和四年(2022年)の連載企画として紹介して生きている「愛知県下新十名所巡り」も早いもので第7弾となります。今回は名古屋市中区丸の内三丁目という名古屋市の中心地にある「京町薬祖神」を中心に巡っていく事にします。何度も愛知県下新十名所の紹介記事の中で紹介していると思いますが、愛知県下といいつつ名古屋市内の名所については殆どノミネートされていません。これは愛知県下新十名所選定以前の大正十四年に「名古屋新十名所」が選定された事が影響しているのは間違いないかと思います。 名古 ...
名所沿革
相生山は名古屋市東部の天白区に広がる丘陵を指す。この丘陵は「鳴海丘陵」とも呼ばれ、メタハロイサイトと呼ばれる古赤黄色をした粘土層で構成されていた。この粘土質の土が焼き物に適してたからか相生山周辺には古来からの陶器(須恵器)を焼くための窯跡が点在していたとされ、相生山周辺の山々の木々は燃料として伐採され、相生山はいたるところが「はげ山」となっていて、赤黄色の地肌がむき出しになっていたという。 ・・まあ、愛知県は日本三大ハゲ山県の一つで明治時代以降大規模な緑林が行われる前は県下の山々はハゲ山だらけだったそうですが・・。
明治時代になり、この相生山周辺は名古屋市中からも程よい距離にあるとして開発が行わる事となり、周囲を「文化村」として分譲が行われ、さらに高さ百二十尺十二段の塔、その頂には黄金の釈迦牟尼仏を建立、その周囲に四国八十八ヶ所の弘法大師霊場が開創された。
明治期から昭和初期にかけて名古屋市のベッドタウンとして開発が行われていった相生山は古くからの名所・旧跡という性格ではなく、新たな土地開発の雄として名古屋新十名所に登録を目指して相生山のある野並の人々は相生山の山頂に本部を置き日夜投票を呼び掛けていたと伝えれています。その苦労もあり、852,631票もの投票を集め堂々5位に入選しています。
ポイント
平成となり、周囲の渋滞解消を目指して相生山を横断する県道が整備されることになりましたが、河村市長が当選し工事が8割過ぎまで進んだ県道工事の事業を廃止する事を決定し、相生山全体を「世界のAIOIYAMA」と銘打って公園化する意向を示しているそうですが、河村市長が退任した後、道路推進の市長が当選したら一気に道路工事事業の再開が行われそうです。それくらい道路工事の進捗状況は進んでいるわけです。
名所訪問
相生山自体は非常に広いエリアとなっていて、ここが相生山!という場所が存在しないのですが、まあ名古屋市の東側に広がる自然豊かな丘陵地が相生山という認識で間違っていないかと思います。
葉書供養塔

そんな相生山ですが、愛知県下新十名所を感じさせてくれる場所が二ヶ所点在しています。まず一つ目は、愛知県下新十名所を決定する投票戦においれ投票に使われた葉書を集めた「葉書塔」になります。どういった経緯でこの相生山に投票で集まった葉書をおさめた塔が建立されたのかは不明ですが、愛知県下新十名所が決定した後の昭和三年に葉書をおさめた「葉書塔」が建てられます。その後は、太平洋戦争を経て戦後復興、高度経済成長などの時代の変遷の中忘れられた存在となっていましたが、昭和六十二年に修復され「葉書供養塔」として修復され、毎年、相生山の開発に尽力したという徳林寺にて法要が行われているようです。

修復されたという事で元々の形は当時のままだと思われる葉書供養塔。五角形の非常に変わった形状をしています。修復の際に前面に埋め込まれた仏像が供養塔であることをしめしています。葉書の状態がどうなっているのかは不明ですが、今後昭和初期の愛知県の様子を窺い知る事の出来切る貴重な史料となっていくのかもしれませんね。

供養塔の脇に建てられた石碑は、昭和三年にこの場所に愛知県下新十名所の投票戦で集まった葉書を保存する塔を建立した旨を記しています。この石碑によると、投票総数は二千万以上、この葉書に書かれた候補地は三百ヶ所以上にのぼったようです。令和四年現在の愛知県の人口が七百万ほどと考えると、現在の人口でも一人三票を投票した計算になる訳で、現在より人口が少なかったであろう当時の熱狂ぶりがこの辺りからも感じ取れます。
相生山徳林寺

大正十二年、高岡徹宗が相生山を観光地として開発するにあたり、石川県より徳林寺を移したことが創建とされる曹洞宗の寺院になります。徳林寺のHPを拝見させて頂くと、「曹洞宗の大本山である総持寺(明治三十一年に焼失)を復興、鶴見に移転させ総持寺の中興と呼ばれる「石川素堂禅師」によって明治時代に開かれた。」としています。史料がないので勝手な想像ですが、もしかしたら、徳林寺は明治三十一年に総持寺の延焼した時に同時に焼失した塔頭の一つで、石川素堂禅師により復興が行われ、その後大正になり相生山に移ったのかもしれませんね。

現在の住職は十年ほどネパールで過ごしていた事もあり、現在の徳林寺は曹洞宗の寺院なのですが、本堂前にはタルチョと呼ばれるチベットの寺院などでよく見られる五色(青・白・赤・緑・黄)の祈祷旗がはためいています。このタルチョがはためいているだけで多国籍チックな雰囲気なるのですが、どうやらチベットや東南アジアの方が来日されて修行されているようです。
愛知県新十名所 石標柱

徳林寺本堂の手前に「愛知県下新十名所 野並相生山」と彫られた石標柱が建てられています。ここ徳林寺は先に紹介した葉書塔が昭和三年に建てられた時にその場所を提供したそうです。相生山の開発事業に徳林寺は深く関わっていた事がこの辺りからも感じられます。

この石標柱は葉書塔が建てられたと同時に建てられたと思われ、たぶんここの石標柱だけが新愛知新聞社自らが建てたものだと思います。

もう一つ徳林寺が多国籍の雰囲気を感じる要因となっているのがこの東南アジア様式となる八角形の鐘楼になります。日本の鐘楼とは明らかに様式がことなっていますね。
相生山神社

葉書塔のある場所から、たぶん大正時代から昭和にかけて分譲されたのであろう緑に囲まれた分譲地を西に進んでいくと、この相生山周辺の鎮守であろう「相生山神社」が鎮座しています。詳細は不明ながらこの相生山に住んでいる人たちを見守っている神社なんだろうなと思います。

境内には社が二基鎮座しており、向かって大きい社が相生山神社の本殿だと思います。御祭神など全く分からない神社ですが、これからも相生山に住む人たちの崇敬を集めていく神社であってほしいなと思います。
相生山観音

相生山神社の西隣には相生山の開発の中でこの山中に安置されていた観音像を集めたんだろうと思われる相生山観音菩薩の呼ばれる観音堂があります。
今でこそ相生山緑地として整備が進んでいますが、大正期から昭和初期にかけては宗教色が強い開発が行われていたのは先に紹介した通りだったりします。それらがいったいどこに建っていてどうなったのかは全くの不明ですが、この観音像たちは当時の相生山を見てきたのではないでしょうか。
所在地を地図で確認
| 名所名 | 野並相生山(相生山緑地) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区天白町野並地内(GoogleMap) |
| 最寄駅 | 電車:名古屋市営地下鉄 桜通線「相生山駅」徒歩11分 バス: |

















