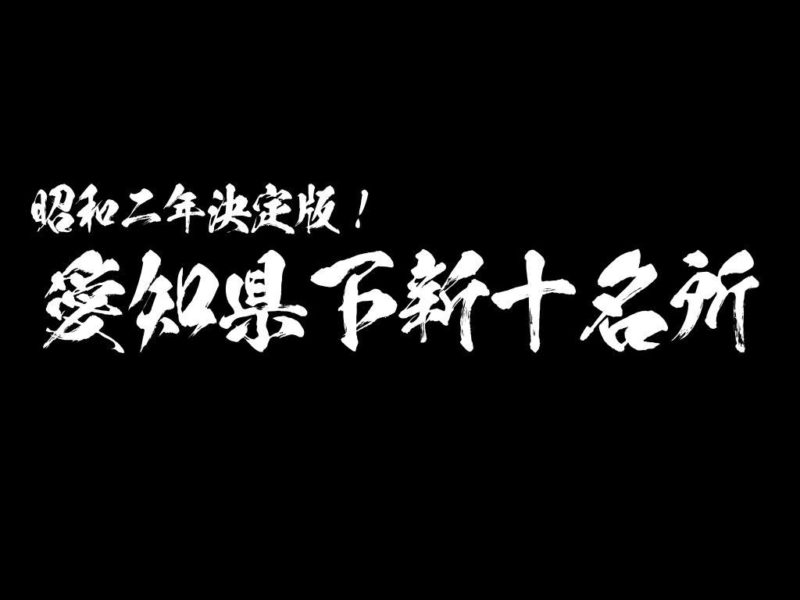寺院紹介
寺院概要
| 寺院名 | 松洞山龍泉寺 |
| 所在地 | 名古屋市守山区竜泉寺一丁目九〇二番地(Googlemap) |
| 創 建 | 延暦年間(792-806年) |
| 宗 派 | 天台宗 |
| 御本尊 | 馬頭観音 |
霊 場
| 霊 場 | 尾張三十三観音 二十五番札所 名古屋四観音 |
| 前札所 | 霊 場 | 次札所 |
|---|---|---|
| 龍音寺(小牧市) | 尾張三十三観音 | 宝泉寺(瀬戸市) |
文化財
| 国 宝 | |
| 国指定 | 仁王門 木造地蔵菩薩立像 |
| 県指定 | |
| 市指定 町指定 村指定 | 木造馬頭観音および熱田大明神・天照皇太神立像 |
参拝情報
| 御朱印 | 〇 |
| URL | 〇/https://www.ryusenji.com/ |
| 駐車場 | 〇 |
| 参拝日 | 2022年4月20日 |
御由緒
宝暦五年(1755年)に記された「龍泉寺記」によると「伝教大師が熱田神宮に参篭中、龍神の御告げを受け、龍の住む多々羅池のほとりでお経を唱えると、龍が天に昇ると同時に馬頭観音が出現したので、これを本尊として祀った。」と記されていおり、伝教大師(最澄)を開基とする寺院であるとしています。
また、大正十二年発刊された東春日井郡誌では、「延暦年中(792-806年)に伝教大師熱田宮に参籠して、修法ありたるとき、即ち龍神の告によりて此地に来り。多羅々が池より出現してある閣浮檀金の馬頭観音の像を安置せんして、以て茅堂を営みあり。」と記しており、龍泉寺記に沿った内容を紹介しています。537
戦国時代には、豊臣秀吉と徳川家康が戦った「小牧長久手の戦い」において、この龍泉寺周辺に豊臣方が砦を築き、この砦を徳川方が攻め込んだ為、豊臣方は退却の際に火を付け龍泉寺の伽藍は焼失してしまったといいます。慶長三年(1598年)に伽藍は再建されています。
明治三十九年(1906年)に龍泉寺は放火に遇い、多宝塔、仁王門、鐘楼を除く全てが灰燼に帰してしまいます。しかし、竹あとから「慶長小判百枚」が発掘された為、これを再建の基金とし更に多くの御信者の寄付があり、本堂などが再建されています。
参拝記
新交通システムの名古屋ガイドウェイバス(ゆとりーとライン)の終着駅である「小幡緑地バス停」から県道15号線を志段味方面に200mほど進むと龍泉寺の境内に向かう参道が見えてきます。信号のない交差点なので、特に志段味方面から龍泉寺に向かう際は右折となるので注意が必要です。
県道15号線から続く参道の様な市道を進んでいくと、突き当りに龍泉寺の境内が見えてきます。駐車場は向かって右手側に用意されていますので安心して車で向かう事ができます。
境内入口

龍泉寺の境内入口には中々他の寺院では見かける事が少ない「狛犬」が参道脇に一対鎮座しています。この辺りは熱田神宮の奥之院とも称されていた時代の名残なのでしょうかね。

かなり独創性のある狛犬の様な気がしますが・・。今まで紹介してきた狛犬とは違う雰囲気を自分的には感じていますが、皆さんはどうですか?
仁王門(国:重要文化財)

江戸時代の再建当初の姿を今に伝えるという八脚楼門づくりの仁王門になります。明治時代の放火によって本堂などが消失してしまわなければ龍泉寺全体が重要文化財に指定されていてもおかしくなかったのかもしれませんね。


左右の間部分に鎮座する仁王像も江戸時代作の様です。
多宝塔

元々は大日如来像が安置されていたそうですが、由緒の所でも紹介していますが小牧長久手の戦いの際に焼失、その後再建されており、現在では阿弥陀如来像が安置されているそうです。
寺院の伽藍配置では本堂向かって右手側に多宝塔などの塔を据える配置が多いそうですが、江戸時代以降、大修理を行う際に本堂向かって左手側に移設され、明治の放火の際には消失を免れた江戸時代の多宝塔の造りを今に伝えています。
岡崎周辺の多宝塔は朱塗りされていない素地むき出しの造りの物が大多数であり、こうした朱塗りの多宝塔は非常に新鮮な気分にさせてくれます。岡崎周辺の多宝塔と言えば・・・。
本堂

入母屋造瓦葺妻入りの瓦破風の向拝が設けられた本堂になります。本堂も多宝塔と同じ白壁に朱塗りの柱という彩色となっているのが特徴です。

両建物を一堂に見ると、非常にバランスの取れた彩色になっている感じがします。
東門

木々に日の光が遮られてしまいかなり暗い感じとなってしまい、細部がよくわかりませんが、門扉の無い高麗門の東門となります。東門から先は石段が伸びており、観光バスなどの駐車場へ向かう事が出来ます。この東門から石段を下りていくと・・・

天台宗の寺院なのに、真言宗開祖である弘法大師の霊場である新四国霊場が開創されていました。かなり古くからここに開創された新四国霊場の様です。こうして宗派を超えて信奉されているのも弘法大師のすごさなのかもしれませんね。
水野房次郎・篠田銀次郎 寿像

はっきりとその名が彫られている訳ではないようなのですが、この両氏の像については、コンクリート像作家としてその名を知られている「浅野祥雲」氏の作ではないかと考えられているそうです。
写真左側の銅像は「水野房次郎」氏、右側の銅像は「篠田銀次郎」氏の像になります。両氏共に名古屋市における畜産業に貢献をされた方だったようです。「名古屋牛馬畜産組合」の名を確認できたことから、この組合に関係された方だと思われます。
御嶽教



龍泉寺周辺には先に紹介していますが新四国霊場の札所が点在しているのですが、その札所に沿って少し山道を登っていくとその先に御嶽教の神社が鎮座していました。妻入り開放型の拝殿を有する社殿とその脇に数多くの石碑が建てられた御嶽教特有の施設が設けられています。ここは龍泉寺が管理しているのかは不明ですが、ここで紹介させて頂きます。
参拝を終えて

龍泉寺の境内には非常に多くの猫たちがのんびりと日向ぼっこをしていました。まったく逃げる事もない事からかなり人懐こい子たちのようです。

個人的には猫派なんで、こうした猫たちを間近で見れるとめっちゃ嬉しくなっちゃいます。
遊び予約/レジャーチケット購入サイト「asoview!(アソビュー)」
所在地を地図で確認
| 寺院名 | 松洞山竜泉寺 |
| 所在地 | 名古屋市守山区竜泉寺一丁目九〇二番地(Googlemap) |
| 最寄駅 | 鉄道: バス:名古屋ゆとりーとライン「小幡緑地バス停」徒歩8分 |