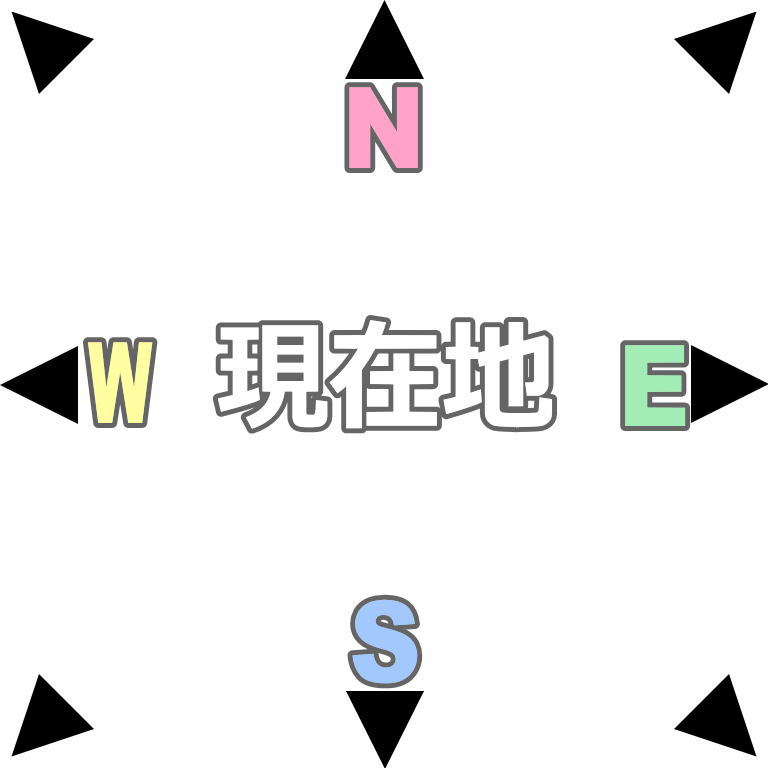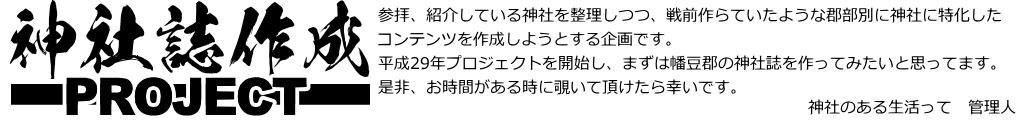神社情報
神社名:神明社
鎮座地:西尾市横手町溝東六十番地
御祭神:天照大御神
旧社格:神饌幣帛料供進指定村社
創 建:永正三年(1506)三月十五日
境内社:千川社、御鍬社、千間社、稲荷社
例大祭:十月十五日
御朱印:ー
H P:ー
参拝日:2010年10月24日
参拝日:2017年10月31日
御由緒
社伝に、永正三年(1506)三月十五日の創建という。伊勢の人、横井貞助、この地を開拓し守護神として祀る。その後鳥井太郎八が新田を譲り受ける。開祖の片名をとり横貞にしたが横手に変わった。明治五年十月十二日、村社に列格する。昭和十二年六月二十二日、神饌幣帛料供進指定をうけた。同四十七年十月、拝殿改築、渡殿を新設した。
愛知県神社庁 発刊
「愛知県神社名鑑」より
當社は後柏原天皇御字永正三年三月十五日今より四百六十七年前、横井貞助なるもの当地の新田を開拓し成功の後之を鳥井太郎八に譲りて更に新田開拓のため自ら勢州に移り故に同士の片名を取り横貞と呼びしより地を横手を称するに至る。當社の創立は新田開発と同時ありしものあり。
昭和十年六月十八日付 指定村社に列す。
同時に 神饌幣帛料供進神社に指定
昭和四十八年四月吉日
境内「御遷宮記念碑」より
参拝記
矢作川右岸、愛知県道41号西尾幸田線から南側を横手町というそうで、その横手町集落のほぼ中心位置に鎮座しているのがこの神明社になります。集落の方以外はそうそう通らない道沿いに鎮座しているので、田園風景が広がる地域ですが、神社の存在に気付いている方はそうそういないのかな?と思ったりします。
境内前の道路を挟んで反対側に幟立石が立ち並んでいます。こんな神社前に幟立石が密集している場所はあまり見かけないですねえ。
ストリートビューで神社周辺の雰囲気を感じて下さい。
境内入口
石垣で盛土され、玉垣で囲まれた境内です。境内は公園としても使用されているので、非常に開放的な雰囲気があります。
社号標
愛知県知事によって書かれた社号標になります。
桑原幹根氏は、1951年5月に愛知県知事選挙に当選し、以後1975年2月まで、6期連続、24年にわたって愛知県知事を務めたという方です。愛知県初の名誉県民にもなられています。
鳥居
神明鳥居がお出迎え。建立年月を調べ忘れました・・・。
手水舎・水盤
四本柱タイプの木造瓦葺の手水舎になります。
狛犬
昭和十四年七月生まれの子乗り、玉乗りの狛犬一対
社殿
改めて社殿を望みます。
入母屋造、瓦葺、平入、高覧付きの廻縁の設けられた拝殿になっています。
どういう造りなのかは不明なんですが、廻縁部分はコンクリート造りになっていて、廻縁全体が基礎の様になっています。
これだけで、同じような造りの神社とは異なった雰囲気になっています。
本殿は覆殿になっているそうで、中には神明造の本殿が鎮座しているそうです。拝殿と覆殿の間に渡殿が昭和四十七年が新設されています。元々は露天祭場だったんでしょうね。
境内社
社殿向かって左手に鎮座する、千川社、御鍬社、千間社、稲荷社の相殿になります。この境内社の鳥居は元文五庚申年(1740年)に建立されています
懸魚・鬼瓦
なかなか立派な造形の鰭付きの蕪懸魚になります。
記念碑
なかなか立派な遷宮記念碑。
参拝を終えて
創建500年を超える神社になります。矢作川右岸堤防からもみえるくらい近い場所に鎮座しています。社殿も矢作川に向かって経っている様にも見え、治水の願いも込められているのかな?と思います。江戸時代にあり、放水路として今の矢作川が作られるまで、洪水を繰り返していたとはずですので、治水の祈りはこの辺りに住む人たちの総意だったんでしょうね。
近隣の神社